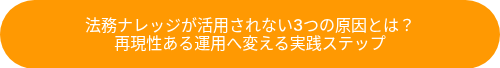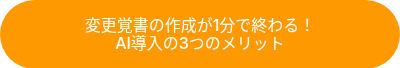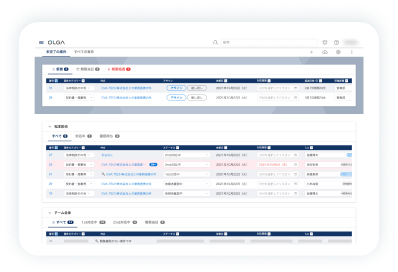法務コラム
- 未来を切り拓く攻めの法務、守りの法務- 法務部の更なる進化に向けた人とテクノロジーの戦略とは
投稿日:2025.07.31
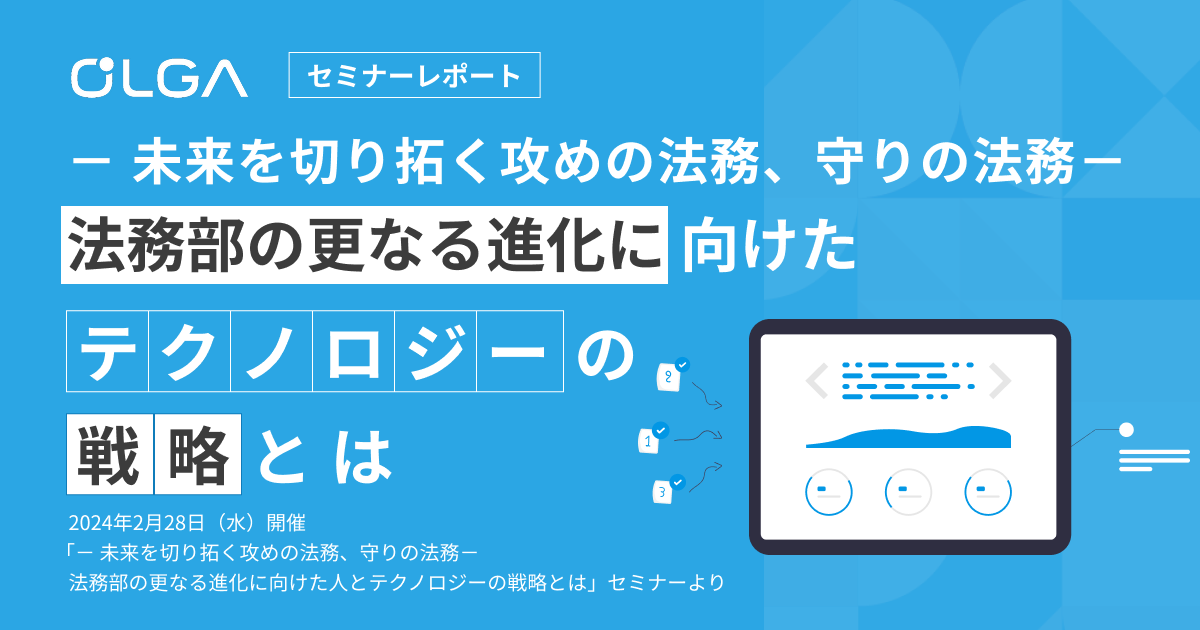
※本記事は、2024年2月28日(水)に開催した「- 未来を切り拓く攻めの法務、守りの法務- 法務部の更なる進化に向けた人とテクノロジーの戦略とは」のセミナーレポートです。
本セミナーでは、企業法務部門が直面する外部環境の大きな変化と、それに伴う役割の拡大、そしてリソース不足という複合的な課題に対し、いかにして対応し、さらなる進化を遂げるかについて解説しました。
とくに、「攻めの法務」と「守りの法務」のあり方を再定義し、それらを実現するための具体的な方策やリーガルテック活用、人材戦略について、株式会社Legal Innovation Lab 代表取締役 弁護士 服部氏より具体的な事例を交えながら提言が行われました。
目次
法務部門の現状と直面する課題
まず法務部門を取り巻く現状として、以下の点が挙げられます。
外部環境の大きな変化
- 法改正の頻発化・複雑化、グローバル化の進展など、法務部門が対応すべき範囲が拡大
- 社会全体のコンプライアンス意識の高まりにより、企業に求められる法的要求水準が上昇
- テクノロジーの急速な進化は、新たな法的論点やビジネスモデルを生み出し、法務部門の対応を迫っている
求められる役割の拡大
- 従来の契約管理やコンプライアンス対応といった「守りの法務(ガーディアン機能、ナビゲーター機能)」に加え、新規事業のリーガルサポートやビジネスモデル構築への貢献といった「攻めの法務(エクスプローラー機能)」の重要性が増している
- 具体的には、新規事業における法規制調査、当局との折衝、M&A対応、知的財産戦略などが挙げられる
法務リソースの逼迫
- 業務範囲が拡大する一方で、法務人材の採用は困難を極め、多くの企業で人材不足が深刻化
- 採用後の育成にも時間を要し、即戦力化が難しい
- 予算的な制約も課題となっている
「負のループ」の発生
- リソース不足の中で業務量が増加し、残業時間の増加や目の前の業務処理に追われる状況が発生
- これにより、中長期的な視点での業務改善や戦略策定が後回しになり、ミスが増加
- 結果としてさらにリソースが割かれ、状況が悪化するという悪循環に陥る企業も少なくない
- このような状況は、従業員のモチベーション低下や離職にも繋がりかねない
課題解決のための方策:「攻めの法務」と「守りの法務」の再定義とバランス
これらの課題を克服するためには、まず現状を正確に把握し、組織として明確な「方策」を打ち出すことが極めて重要です。その上で、「攻めの法務」と「守りの法務」のあり方について、以下のように整理します。
守りの法務:リスクを未然に防ぎ、事業継続の基盤を固める
「守りの法務」とは、企業活動に伴う様々な法的リスクを未然に防止・低減し、コンプライアンスを遵守することで、事業の安定的な継続と企業価値の維持を図る活動を指します。以下の具体的な業務内容と戦略例が挙げられます。
- 主な業務内容
- 契約審査業務: 取引に伴うリスクを洗い出し、不利な条項を修正するなど、企業の権利を守るための基本的な業務です
- 知的財産権の侵害対応: 他社からの権利侵害に対する警告や訴訟対応、逆に他社の権利を侵害しないための調査や予防策を講じます
- 業務プロセスの構築・徹底: 法務審査プロセスにおける事業部との連携強化や、各種業務フローの標準化・効率化を通じて、リスク管理の質とスピードを向上させます
- 就業規則・雇用契約書等の整備: 労働基準法をはじめとする関連法規の改正に対応し、適切な労務管理の基盤を整備します。近年ではフリーランスや業務委託など多様な働き方に対応した契約形態の整備も重要性を増しています
- コンプライアンス対策: 各業種に特有の業法改正に迅速に対応し、事業の適法性を常に維持します。また、ハラスメント防止研修の実施や内部通報制度の適切な運用など、社内のコンプライアンス意識向上と体制強化を図ります。特に、法改正のスピードが速く、昨日まで適法だった事業が違法となるケースもあるため、継続的なインプットと対策が重要です
- 法務監査: 既存のビジネスモデルや社内体制、特に労務関連の規定や運用が、現行法に照らして適法かつ適切であるかを定期的に監査し、潜在的なリスクを早期に発見・是正します
- 戦略例
- 法令遵守プログラムの全社的実施: 特定の部門だけでなく、全従業員を対象としたコンプライアンス研修や啓発活動を計画的に実施し、組織全体の遵法意識を高めます
- インシデント発生時の対応プロセスの事前策定: 情報漏洩や不祥事など、有事の際に慌てず迅速かつ適切に対応できるよう、具体的な対応手順、責任体制、広報方針などを事前に明確化しておきます
- データ・知的財産管理に関する全社的啓発: 個人情報保護法や知的財産権に関する知識・意識を法務部だけでなく全社的に高め、日常業務におけるリスク管理を徹底します
攻めの法務:事業成長を積極的に後押しし、新たな価値創造に貢献する
「攻めの法務」とは、法的な知見や戦略を積極的に活用し、企業の事業拡大、新規事業の創出、競争優位性の確立といった目標達成を法務面から能動的に支援する活動を指します。単にリスクを指摘するだけでなく、事業部門と共に解決策を模索し、ビジネスの成長を加速させることが期待されます。以下の具体的な業務内容と戦略例が挙げられます。
- 主な業務内容
- 新規事業立ち上げ時の適法性審査とリスク分析: 新しいビジネスモデルやサービスが既存の法規制に抵触しないか、どのような法的課題があるかを早期に洗い出し、事業部門にフィードバックします。新規性が高い事業の場合、法規制が未整備なグレーゾーン領域で事業を進めざるを得ないケースもあり、その際には規制当局の見解を確認したり、サンドボックス制度のような仕組みを有効活用したりしながら、事業実現の道筋をつけることが重要です
- 海外進出支援: 進出先の国・地域の法制度、商慣習、紛争解決手段などを調査し、現地法人設立、契約交渉、コンプライアンス体制構築などを法務面からサポートします
- M&A対応: デューデリジェンス(法務監査)、契約交渉、クロージング、PMI(買収後の統合プロセス)における法的課題への対応など、M&A戦略の実行を法的に支援します
- 行政・立法への働きかけ(ロビイング活動): 現行の法規制が新規事業やイノベーションの障壁となっている場合、業界団体等と連携し、規制緩和や新たなルール形成に向けて行政機関や立法府に働きかけることも、攻めの法務の重要な役割となり得ます
- 知的財産権の戦略的利活用: 自社の技術やブランドを国内外で適切に保護し、ライセンス供与や共同開発などを通じて収益化を図るなど、知的財産を経営資源として積極的に活用するための戦略を策定・実行します。特に海外進出時には、国ごとに異なる法制度や商慣習を踏まえた知財戦略が不可欠です
- 戦略例
- 新規市場参入・製品販売時の法的状況担保策の提言: 事業部門が新たな市場や製品で成功できるよう、法務部門から積極的に法的リスクを低減し、事業機会を最大化するための具体的な提案を行います
- 新規事業におけるクリティカルな知的財産権の保護戦略策定: 他社の既存権利を侵害していないかの調査はもちろんのこと、自社の技術やアイデアを核となる知的財産権として早期に確保し、模倣を防ぎ、競争優位を築くための戦略を立案します
- 定型的な契約業務の処理パターン確立: 頻繁に発生する種類の契約については、リスク許容度に応じた複数の標準雛形を用意したり、チェックポイントを明確化したりすることで、レビューの迅速化と質の標準化を図ります
- 最新デジタルツール(生成AI等)の業務活用探求とマニュアル化: 生成AIのような新しいテクノロジーを法務業務にどのように活用できるか(契約書ドラフト作成補助、リサーチ補助など)を積極的に検討し、利用する際の注意点(知的財産権侵害リスク、個人情報保護など)を踏まえた社内ルールやマニュアルを整備します
バランスの重要性
「守りの法務」と「攻めの法務」のどちらか一方に偏るのではなく、自社の事業フェーズ、経営戦略、企業文化、そして利用可能なリソースを踏まえ、双方のバランスを考慮し、どこに力点を置くべきかを判断することが肝要です。例えば、創業期や成長初期の企業であれば、事業を積極的に拡大するための「攻めの法務」の比重が高まるかもしれませんが、成熟期にある企業や規制業種においては、コンプライアンス遵守やリスク管理といった「守りの法務」の基盤をより強固にすることが求められるでしょう。重要なのは、自社の状況を客観的に分析し、最適なバランスを見つけ出すことです。
方策を講じるための時間創出と具体的なステップ
「攻めの法務」「守りの法務」を実践するためには、まずそのための時間を創出することが急務であり、ステップとしては以下の通りです。
1.業務プロセスの洗い出
まず、法務部門が現在どのような業務にどれだけの時間と労力を費やしているのかを客観的に把握することが出発点となります。契約審査の件数、各案件の処理時間、定型業務と非定型業務の割合、問い合わせ対応の頻度などを具体的に洗い出します。
2.課題・原因の特定
次に、洗い出された業務プロセスの中で、特に時間がかかっているボトルネックとなっている箇所や、非効率な部分、リスク管理上の課題などを特定します。例えば、「契約書の標準雛形が存在しないため、案件ごとにゼロから作成している」「事業部からの依頼時の情報が不足しており、手戻りが多い」「過去の類似案件のナレッジが共有されておらず、調査に時間がかかる」「チェック体制や承認フローが複雑すぎる」といった具体的な原因を深掘りします。
3.具体的な解決策の検討・実行(時間創出のため)
特定された課題と原因に対して、業務効率化と時間創出に繋がる具体的な解決策を検討し、実行に移します。これには、リーガルテック(電子契約システム、契約書レビュー支援ツール、案件管理システムなど)の導入検討、既存のITツール(チャットツール、RPAなど)の活用、業務マニュアルや標準雛形の整備、事業部への教育・啓発による依頼品質の向上などが含まれます。このステップの主目的は、日々のオペレーショナルな業務負荷を軽減し、より戦略的な業務に取り組むための「時間」というリソースを生み出すことです。
4.方策の立案
上記ステップによって創出された時間を活用し、ここで初めて、自社が目指すべき法務の姿、すなわち「攻めの法務」と「守りの法務」の具体的なバランスや、それぞれの領域で取り組むべき中長期的な戦略・施策(方策)を立案します。この段階では、自社の経営戦略や事業フェーズ、リソース状況、そして洗い出された法務課題などを総合的に考慮し、優先順位をつけながら、実現可能なアクションプランに落とし込んでいくことが重要となります。この「方策を立案する時間を確保すること」こそが、負のループから脱却し、法務部門が進化するための最初の、そして最も重要な一歩です。
まとめ
本セミナーは、現代の法務部門が抱える多岐にわたる課題を浮き彫りにするとともに、それらに立ち向かうための具体的な思考のフレームワーク(攻めの法務・守りの法務のバランス、時間創出のステップ)と、それを支援するソリューション(人材戦略、リーガルテック活用)を提示する、示唆する内容でした。特に、リソースが限られる中でいかに戦略的な時間を確保し、企業の成長に貢献する法務へと進化していくかという点が重要です。
法務部門のご担当者様にとって、自社の法務機能の現状を見つめ直し、今後の変革に向けた具体的なアクションを検討する上で、有益な情報となれば幸いです。
▼本セミナーのアーカイブ動画はこちらからご視聴いただけます。
https://olga-legal.com/seminar/offensive-and-defensive-legal20240228/