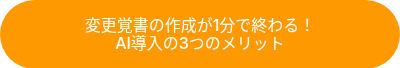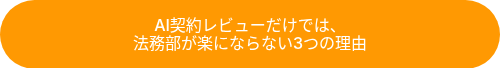法務コラム
【イベントレポート】弁護士のための 生成AI実践コミュニティ 「“机の上”からはじめる収益向上の第一歩」 ~せきらら生成AIトーク×弁護士同士のリアル交流~
投稿日:2025.07.11

登壇者(左:法律事務所Verse代表 金子弁護士 右:GAMBA法律事務所代表 竹波弁護士 )
👉弁護士のための生成AI実践コミュニティへの参加はこちら(無料)
1.「弁護士のための生成AI実践コミュニティ」
当コミュニティは、弁護士にとっての依頼者となり得る、あらゆる人が生成AIを広く利用し、時にその回答に振り回されてしまうこともあるこの現代社会で、弁護士が、依頼者のために、社会のために、そして弁護士自身のために、生成AIに関する「実践」的知見を学び合う「場」を創り出すことを目的として、立ち上げられました。
当コミュニティのFacebookグループはもうすでに210名を超えており、そこでは質疑応答がなされ、毎朝の”プロンプト答練”やpodcastの企画も進んでおり、今後、オンライン、オフラインともに、全国各地での実施を予定しております。
オンラインでの勉強会は参加者5名から無料で実施いたしますので、参加・協力いただける弁護士の方はぜひご連絡ください(なお、5名未満の場合でもご相談は可能です)。
本レポートは、30名を超える弁護士(東京、埼玉、愛知から参加)が参加した初のオフライン会(コミュニティメンバー限定)の記録であるとともに、ここで得られた知見をより世に広めることを目的として作成されました。
2. 法律業務におけるChatGPTとGeminiのアウトプットに関する議論
オフライン会では、一般的なセミナー形式でなく双方向対話型のスタイルで実施が行われ、まず、代表的な生成AIであるChatGPTとGeminiについて、法律業務でどういった活用ができるのか、実際にどう活用されているのか、という点が話題の中心となりました。
2-1. 文章生成の思想と品質:なぜGeminiは自然な文章を生成するのか
生成AI時代初期の頃から弁護士業務においてAIを活用されていた登壇弁護士は、ChatGPTやGeminiの進化の流れ、特に文脈を保持したまま自然な文章を生成する能力の進化について、まず解説。
これは、Googleが長年SEOなどで培ってきた「ウェブ上の良質な文章」を深く学習していることが背景にあるのではないか、との分析も紹介されました。
一方、ChatGPTの文章は、時に要素を分解して書き出すような特徴があり、法律家が作成する文章のニュアンスとは異なる場合があるとの指摘もありました。
2-2. 実践比較:契約書作成に見るアウトプットの具体的な差
コミュニティのテーマは「弁護士による生成AIの実践」。
時間が進むにつれ、より具体的な話に入っていき、まず契約書作成や審査のタスクをどのように生成AIで行うか実演がなされました。
登壇弁護士によると、ChatGPTに契約書を作成させると、法律家であれば通常用いないような言い回しや、不自然に短い条項が生成される傾向が見られたとのことで、その実演がされました。
一方、Geminiは、より実際の契約書に近い、実務でもある程度通用するレベルの条項を生成することができると評価され、これも実演。
このアウトプットの質の差が、発表者が法律文書作成という局面において、Geminiを主に使用する理由の一つであると語られました。
このように、コミュニティの目的である「実践的活用術の共有」に即し、様々な実演がされました。
👉弁護士のための生成AI実践コミュニティへの参加はこちら(無料)
3. Google Drive連携による業務効率化の可能性
また、プロンプトの実演のみならず、生成AIによる具体的な業務効率化術の一例として、Google Drive内のドキュメントとGeminiを連携させるデモンストレーションが行われ、その実用性に注目が集まりました。
3-1. デモンストレーションで示された複数ファイルの横断分析
デモンストレーションでは、特定のフォルダに保存されている複数のPDFファイルをAIに一括で読み込ませる方法も実演されました。
従来であれば、一つ一つファイルを開いて確認する必要がありましたが、この方法を使えば「このフォルダにある○○資料の合計金額は?」と自然言語で指示するだけで、AIが各ファイルの内容を横断的に読み取り、読み取った情報に基づき数値の合計金額を即座に算出したり、アウトプットが瞬時に出ることも実演されました。
このように、生成AIをそのまま使うのでなく、Google workspaceとの連携などによってより効率的にAIを活用する方法も紹介されました。
3-2. 「計算が苦手」は過去の話?実務に耐えるAIの進化
かつての生成AIは、正確な計算や数値処理が苦手というイメージがありましたが、デモンストレーションではその精度が大幅に向上している点が示されました。
証拠資料に基づいた損害額の集計や、予実管理表の作成といった、正確性が求められる業務への応用も可能になってきていると登壇弁護士は言います。
この進化により、弁護士がより分析や判断といったコア業務に集中できる環境が整いつつあるという、AI活用の未来像も共有されました。
4. 依頼者のAI利用がもたらす新たなコミュニケーション課題
生成AIが普及したからこそ生じる社会的課題一つとして、昨今依頼者自身が生成AIを手軽に利用できるようになったことで、弁護士とのコミュニケーションに新たな社会的課題が生まれているとの問題提起もなされました。
依頼者自身が生成AIの回答に振り回されかねないこの社会では、弁護士自身が生成AIに対する理解度を高め、弁護士自らが生成AIを使いこなすことが不可欠であることを示しています。
5. 生成AI活用における法的・倫理的論点の整理
「活用を始めたいけど、守秘義務やセキュリティ対策をどう整理すればいいかわからない」といった声も多く聞かれる中、弁護士が業務で生成AIを活用する上で、クリアすべき法的・倫理的な論点についても意見交換が行われました。
特に、依頼者から預かった機密情報や個人情報を含むデータを、外部のAIサービスに入力する際の留意点等もテーマとして扱われました(具体的な内容は割愛しますが、守秘義務とセキュリティ対策について知りたい方は、ぜひこちらの「法律事務所における生成AI活用の倫理的課題と情報セキュリティ対策」(監修:山本 俊、著:康 潤碩)をご覧ください)。
6. おわりに
本レポートで取り上げたような、判断に迷う法的論点や、クライアントとの新たな関係構築、このような複雑な課題に、一人で向き合う必要はありません。
当コミュニティには、同じ問題意識を持つ多くの弁護士がいます。日々生じる疑問も多く投げかけられており、その中でそれぞれの知見を共有し合うことで、変化の時代を乗り越えるための羅針盤となるはずです。
👉仲間と共に、AI時代の法律実務を探求する(コミュニティに参加)(無料)